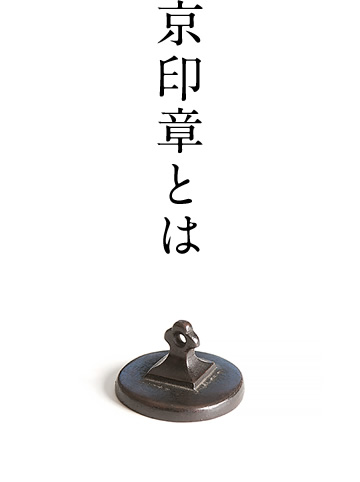我が国で印章(はんこ)が使われるようになったのは、大化の改新により大宝律令が制定されたときからといわれています。平安京以後、京都では天皇御璽(天皇の印章)や当時の役所の官印などが作られて行きました。古代の印はほとんどが鋳銅印で、銅を溶かして鋳造された物でした。やがて鎌倉時代になり宋との交流が盛んとなり僧侶や文人の間に落款印・書物印(絵や書などの作者を示す印)などが流行り益々発展していきました。さらに戦国時代に入ると武将ばかりでなく実名印(後の実印)が使用され商人の間にも普及していきました。江戸時代に入ると庶民にまで印章が広まり印判師が京都に誕生し人数も増えていきました。この様にして京都で発展し作られた印章を京印章といいます。



特色は中国、漢の時代の重厚な作風を受け継いでおり関東の印章と作風が違う事です。そして明治6年10月1日太政官布告で一般庶民も実印の使用が認められるようになり、これを記念して近年10月1日を印章の日と定め、大昔より印章守護の大神、印璽社が奉られている下鴨神社にて印章祈願祭を開催しています。同7年中京区の安部井櫟堂が現在国家の文書に使用されている天皇御璽と大日本国璽を印司に命ぜられ1年がかりで作成しました。その後明治23年には印章の専門家が30軒前後に増え「京都板面彫刻業組合」が設立され現在の京都府印章業協同組合の元になりました。この様な歴史と伝統を受け継ぎ「京印章」は京都の伝統産業として広く親しまれ使われています。


印章の彫り手は心血を注いで一字一句を彫刻します。
その京印章を仕上げるまでの大きな要素が以下の三つではないでしょうか。

- 字法とは、正しく、的確な字か否かを調べる事です。
印章の字体は篆(てん)書、隷(れい)書、楷(かい)書、行(ぎょう)書等が有り、
字体の起源や決まり事などがあり、間違いの無い正しい文字を使わなければなりません。

- 字法で選んだ文字をバランスや太さ、また文字の意味なども考え生きた印章を作り出す。これが章法です。
字画の多い文字や少ない文字、注文される顧客の要望など多様な制約の中から印稿を作り、布字していきます。

- 象牙、水牛、柘植などの印材に印刀を使い彫って行きます。
印刀の切れ味、荒彫り、仕上げの技術度など熟練を要します。
以上の三法以外にも印章の極意は有りますが、大きくは
この字法、章法、刀法を駆使して京印章を作り上げています。


-

- 職種や使用目的にふさわしい書体および字体を選び、推敲を重ねる。書き上がれば作業は半ばまできたといってよい。(章法)
-
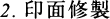
- 印材をよく点検し、印面に朱を塗り慎重に修整を行う。
-
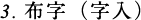
- 印稿の特長をよく生かして、印面に墨で逆に書く。
-

- 布字の通り、霜柱のごとく、テーパーを残らないよう、また深浅のできないように刻る。
-

- 一点一画文字の筆意を生かして奏刀する。(刀法)
-

- 印肉および紙を吟味し、印肉を軽く叩くようにして印面にむらなく付け、慎重に押捺する。(鈐印)